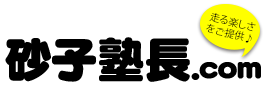第40回:砂子塾長の熱血ドラテク持論

父、砂子義一ストーリー
父・砂子義一が1月3日に永眠。享年87 歳だった。
レースはビジネスではなく、一部のお金持ちの道楽だけだった時代。プロフェッショナルレーシングドライバーという職業がなかった時代……。
日本初のヤマハ契約ライダーとして世界GPへ。その後、4輪に転向し、プリンス、そして、日産ワークスとして走った砂子義一の話をしよう。
義一の子供の頃の『夢』は、ゼロ戦(零式艦上戦闘機)のパイロット。昭和7年生まれ。昭和20年の終戦を13歳で迎える。大阪大空襲を経験し、友達のオ
カンと、その友達の腕を一緒に探した。周りは死体だらけ。空腹で道端の草を食った。
アメリカ軍の大型爆撃機B29が大阪湾に墜落したのを見に行ったという。身体半分が海に浸かり、うなだれたパイロットの腕時計が動いていたのは衝
撃的だったという。
終戦でGHQが街に現れる。『鬼畜米英』のスローガンで育った義一も空腹には絶えられず、「Give me チョコレート!」だったそうだ。
そんな義一少年も思春期になれば、頭の中はバイク、バイク、バイク……。
幼い頃から大好きで、初めての運転は小学生(笑)。近所のオヤジがオート3輪を持っていて、「エンジン掛けられたら乗っていいぞ、坊主」だったって。何とも古きよき時代。
昭和26年、見習いで大阪のスミタというバイクメーカー(当時はまだ4大メーカー以外の企業が多く存在していた)で働き出した。何度もエンジンをばらし、組み立てた。脚が棒になるまで、営業にも出歩いた。
そんな大阪スミタ時代を経て、もともとは楽器屋のヤマハ発動機(戦時中は楽器などの贅沢品をつくることが許されず、軍事部品を製作していた。その工作技術でバイクメーカーへと変化した)で働くことなる。旋盤を扱うことができた義一は、ミッションのメインシャフトを削る仕事に就いた。
昼休みになると、工場の敷地で、バイクに乗ってアクロバットをやっている連中がいた。そこで義一はいった。
「そんなレベルでレースとか、やってるの? オレが乗ったらもっと速い!」
「おい! そこの! じゃあ、勝負するか?」
もれなく真昼の決闘となった。おいおい! 漫画やドラマの話じゃあるまいし……(笑)。もっとも、その決闘が、あっさり義一の圧勝となったのは、い
うまでもない。
1ヶ月間のヤマハ浜松工場での仕事を終え、大阪に戻った義一に、1本の電話が入った。それはヤマハの人事部からだった。
「やべぇ、女の子との遊びが酷過ぎて……人事部から電話か!」
幸いなことに、とんでもない間違いだった。当事のヤマハレーシングチーム監督の渡瀬善三郎氏から指令で、
「あの真昼の決闘の男を浜松に呼び戻せ!」だったのだ。かくして日本初ともいえるプロフェッショナルレーシングライダーが誕生する。
喉から手が出るほど人材を欲しがっていた時代。そのすべてが手探りだった。テストコースを毎日ひた走り、特訓の連続の日々。コーナリング中に起こるエンジンの焼きつきは、何度経験したことか……。
1951年に開催された、第4回富士登山レース。義一は250ccクラスに初出場。初優勝を飾った。そして、それによって、瞬く間にヤマハのエースライダーへと登り詰めるのだった。
1957年、ヤマハワークスライダーとなった2年目。これも、いまでは伝説として語り継がれる浅間火山レース。250ccクラスでワン・ツー・スリー・フィニッシュを果たす。
そして、2輪国産メーカーは海外マーケットの開拓に着手し始めた。レース活動も、世界へと舞台を移していく。
義一が初めて海外を経験したのは戦勝国アメリカ。日本人の海外旅行が制限され、自由には行けない時代。敗戦からわずか16年後の1961年のことだった。1ドル=360円の頃。
ロサンゼルスに降り立った義一は愕然とした。片側5車線の広大なハイウェイ。そりゃ、戦争に負けるわけだ。
海外遠征前には、ヤマハ以外の他メーカーでは、語学やマナー研修があったという。しかし、当時のアメリカのトイレの個室には扉がないのが当たり前だった。大きなハンバーガーを食いながら用を足すアメリカ人たちにマナーなどといわれたくもなかろう(笑)。
さらなる衝撃は、コーラとマクドナルドとケンタッキーフライドチキン(笑)。こんなに美味いモノが世の中にあるのかと……。
「それを日本に持っていくというビジネス的着眼はなかったわけ?」後の息子・智彦(オレ)からの質問に、「そうだな~ オレはセンスねぇ~なぁ~ 思いもよらなかった」と答えた義一だった(笑)
当時の世界的ライダー、マイク・へイルウッドが自家用ジェット機でサーキット入りしたのを見て、「よっしゃ!オレもやったろか!」と思ったという。……買えなかったが(笑)。
とにもかくにも世界GPで欧米を駆け回っていく。1963年7月7日、ベルギーGP、スパ・フランコルシャンサーキットでワン・ツー・フィニッシュ。世界のYAMAHAになった。
日本メーカーの世界GP進出が大成功を収めていく情景は欧米人ライダーとて見過ごせないだろう。1名のライダーの渡航費が100万円を超える時代。そりゃ、欧米人ライダーと契約したほうがいいに決まっている。
その頃、日本では鈴鹿サーキットが誕生。4輪の日本GPが開催される。自動車メーカーがこぞってレースに進出してくる。当時はお金持ちの道楽だったレースにメーカーが出場するために、プロレーサーが必要になったわけだ。
そこでメーカーが目をつけたのが、すでに世界を走っていた日本人ライダーだった。高橋国光、北野元は日産へ。義一、そして伊藤史朗(伝説のライダー、海外からの帰国時に銃を持ち込んで逮捕され、4輪への転向は叶わなかった)、大石秀夫らはプリンスへ。時代は大きく動いていくのだった。
ここからは、多少たりとも、4輪レースファンなら聞いたことがあるだろう『スカイライン伝説』だ。
1964年(この年にオレは生まれる)、第2回日本GPでのスカイライン54B対ポルシェ904、そして、そこから2年の歳月を経て、誕生した富士スピードウェイでの第3回日本GPにおけるプリンスR380の、ポルシェカレラ6を破っての優勝。
そのR380搭載エンジンGR8(2ℓ直6DOHC)から産まれた名機S20が初代スカイラインGT -Rに……。もはや説明不要であろう。
大阪大空襲からモータースポーツの産声とともに時代の波と激動に揉まれた砂子義一。レーサーになんて憧れたことはない。だってプロレーサーがいなかったんだから。
オレがレースを始め、フォーミュラで借金を頼んだことがあった。
「なんでオマエが金払うの?」
「レースは金もらってやるもんだ」と一笑に付された。
高校時代からお小遣いなし。
「食わせる、学校は行かせる」
「遊びたければ自分で稼げ」
義一ならではの教育。最高です。お陰で強い男になりました。
石原裕次郎の歌『我が人生に悔いなし』から……。
鏡に映る我が顔に、グラスを上げて乾杯を。親にもらった身体ひとつで戦い続けた気持ちよさ。長かろうと、短かろうと我が人生に悔いなし。


Revspeedで毎月コラム掲載